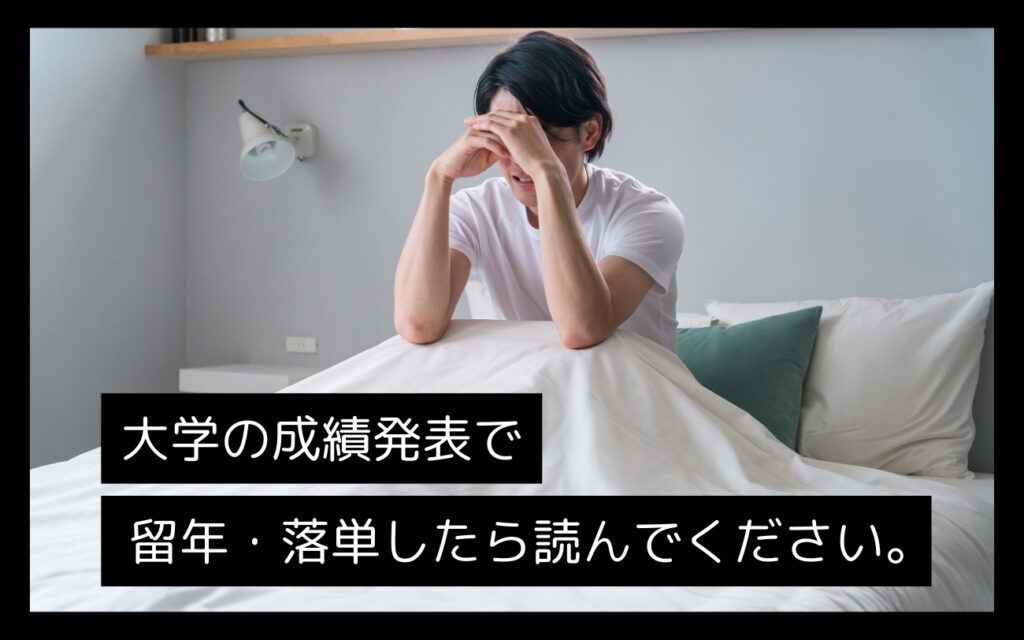
単位を落としたらどうなるのか
そろそろ大学の成績発表の時期です。
(この記事は3月5日に書いています)
期末試験の出来具合が良かった学生にとっては楽しみですが、あまりよくなかった学生にとっては気が重くなる時期ではないでしょうか。
そうは言っても発表された成績には向き合っていかなければなりません。
今回は「単位を落とした大学生」と
「学校からの成績表でお子様が単位を落としたことを知った保護者様」に向けて
「4月までに何をすればいいのか」
「4月からどんなふうに頑張ればいいのか」
について、最初の1歩を紹介をしていきます。
不安な方も多いと思いますが
「1人じゃない!」
と思いながら読んで頂けると嬉しいです。
大学ごとの「成績発表日」の目安
まずは2024年度後期(秋学期)の成績発表日をご紹介します。
※成績発表日の早い順に並べています。
※「2024年度 後期」のため、発表月は2025年2月・3月となります。
「2月発表の大学」
2月13日 芝浦工業大学
2月17日 東洋大学
2月19日 駒澤大学
2月25日 早稲田大学
2月26日 近畿大学
2月28日 法政大学・東京電機大学
「3月1日~3月9日発表の大学」
3月5日 明治大学・立命館大学
3月7日 明治学院大学
3月8日 青山学院大学
「3月10日以降の大学」
3月10日 慶應義塾大学
3月11日 拓殖大学
3月12日 立教大学
※全ての大学は書ききれないので、おおよその目安だと思ってください。
こちらはマイゼミによく相談を頂く大学です。
学校ごとに若干の差はありますが、3月中旬頃には成績が発表されるケースが多いです。
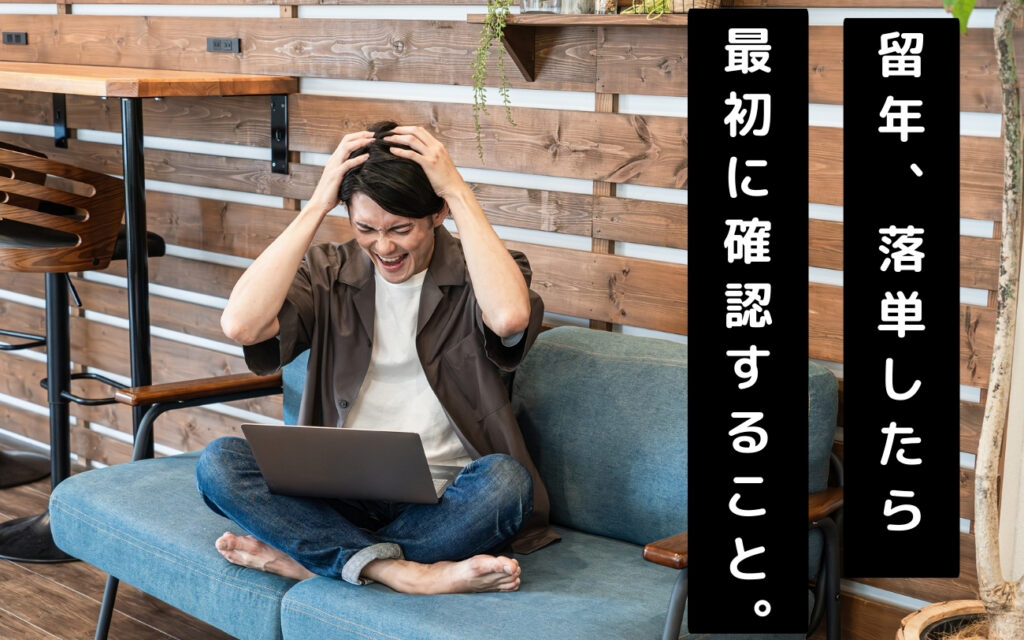
まずは現状の確認をしよう
単位を落としている場合、大学生本人はなんとなく覚悟(予想)していることが多いです。
そのため、成績表をしっかりと確認するのが億劫になってしまうと思います。
しかし、自分の成績表と向き合って来学期からの対策を立てるのが卒業に向けた大事な1歩です。
漠然と「この科目で単位を落とした…」と確認するだけではこの経験を来年に活かせず、メンタルも前向きになりません。
「単位を落とした時に何を確認すべきか」を紹介するので、1つひとつ確認しながら来年に備えましょう!
「いま何をすればいいのか」が分かるだけでも、落ち込んだメンタルが安定することもあります。
①「進級ができるのか」を確認しましょう
この話の前提とはなりますが、大学ごとに進級の条件が違います。
いくつかその例をあげます。
「単位をいくら落としても4年生までは進級できるタイプ」の大学
これは4年までは自動的に学年が上がるが、卒業時に卒業単位数をとれていないと留年するタイプの大学です。
落とした科目を再履修して、4年生の後期までに挽回できればストレート(4年)で卒業も可能です。
最も融通が利く一方で、ギリギリまで危機感を感じにくい側面もあります。
「3年生までは進級できるが、4年に上がるタイミングで規定単位数を取っていないと留年する」タイプの大学
これは3年生までは進級単位の規定がない、もしくはあっても比較的緩いタイプの大学です。
理系大学で「4年になるタイミングで研究室に入る」学部で多いタイプです。
研究室に入る前に必要な単位を取ってね、という意図でしょう。
慶應大学のように3年生からキャンパスが変わる大学・学部もこのタイプになっていることがあります。
「全ての学年で落としていい単位数が決まっている大学」
これはその名の通りです。
規定単位を取れていないと1年生からでも容赦なく留年します。
その分、他の大学よりも再試や追課題などの救済措置を取ることが多いです。
(実際には期末試験を落としてしまう学生は、追試験も1人の勉強では落としてしまうケースが多いです)
このタイプは医療系の大学(医学部・薬学部・看護学部)がほとんどです。
その他にも、卒業時に国家試験が待っている学部はこのケースがあります。
上記のどちらでもありませんが、「東京理科大学」もこのタイプの学部が多いです。
東京理科大学は単位・留年に対してかなりシビアだと感じます。
②「仮進級ができるか」も確認しよう
「仮進級」の制度を取り入れている大学もあります。
仮進級は上の段落で紹介した中では
「3年生までは進級できるが、4年に上がるタイミングで規定単位数を取っていないと留年する」タイプの大学で採用されることがあります。
ざっくりいうと
「本来は研究室に配属するには少し単位が足りないけど、研究室への配属をみとめてあげるよ。研究しながら残りの単位も頑張って取ってね。」
「単位がとれて、規定の研究発表などもクリアできれば卒業を認めるよ」
というものです。
大学によって規定が違ったり、そもそも仮進級制度がない大学もあるのでまずは確認してみてください。

留年した場合
まずは進級規定をクリアできず、留年が決まってしまった人向けの「やるべきこと」です。
不安で頭がいっぱいになると思いますが、落ち着いて現状でのベストを尽くしていきましょう。
まずは落としている科目と分野を確認
(医療系学部以外)
単位を落とすと「落としてしまった…」「どうしよう…」と不安が押し寄せてくると思います。
そうするとその科目のことしか考えられなくなると思います。
しかし、大切なのは
進級・卒業に「どの分野で」「あと何単位必要なのか」です。
大学の単位は大きく「専門科目」と「教養科目」に分かれます。
そして、この専門科目と教養科目もさらに複数の分野に分かれます。
具体例でイメージしよう!
早稲田大学を例に見てみましょう
早稲田大学の創造理工学部経営システム学科は卒業までに「136単位」が必要です。
以下は内訳です。
A群→26単位
B群→22単位
C群→76単位
自由→12単位
〇×群の中でもさらに別れます。
例えばA群の26単位のうち
12単位は外国語(英語)
残りの14単位は複合領域科目
となっています。
複合領域科目の14単位はさらに
「ミクロ経済・マクロ経済の4単位」と「その他の10単位」に分かれます。
「その他の10単位」は数十科目もある中から10単位(ふつうは5科目分)を取ればいいのです。
つまり・・・
この場合は落としたのがミクロ経済・マクロ経済や英語なら再履修が必須になりますが、
それ以外のA群科目なら、「もっと自分が理解しやすい別の科目で単位を取る」ことも選択肢になります。
また授業ごとの時間割の問題もあります。
例えば1年生で落とした科目と2年生で落とした科目が両方とも「火曜日の2限」に設定されている場合、今学期に受講できるのはどちらかか片方のみです。
以上のことから、このタイミグで最初にすべきなのは
「落とした科目を優先度の高い順に整理すること」になります。
大きく分けて
①「もう1回チャレンジすれば取れそうな科目」
②「もう1回チャレンジしても無理そうだが、卒業・進級には絶対必要な科目」
➂「もう1回チャレンジしても無理そうだが、他の科目でも替えが利く科目」
この3つに分けられるといいです。
問題なのは②が多いケースです。
この場合は早めに大学の支援センターや
大学生用の塾の助けを借りた方が良いです。
「無料相談(60分)」などをご利用ください。
逆に留年したものの、①・➂が多ければ早めに対策をすることで自身の努力と友人からの助けで乗り越えれられるケースも多いです。
まずは自分の状況を確認してみましょう!
医療系学部の場合
医療系学部、特に薬学部と看護学部は自分で選択できる科目が少ないです。
そのため、大学側で指定している科目をほぼ取らなければいけないケースが多いです。
医療系大学で留年した学生に最初に確認してほしいことは
①「あと何科目を取れば進級できるのか」
②「来年度に出席する授業は落とした科目だけでいいのか、すべて出席するのか」
この2点です。
とはいえ、この辺りは大学から呼び出され、面談で細かく説明されることが多いです。
必ずメモを取っておき、もう1度チャレンジしても1人では無理と感じたら早めに塾や家庭教師に相談しましょう。
特に医療系学部は卒業後の進路が安定している
ケースが多いので、
「在学中に追加で費用がかかってもなんとか卒業してほしい・・・」
と考える保護者様が多いです。

単位は落としたが
進級はできた場合
単位を落としても進級はできるケースもあります。
落とした単位が少ない場合に多いです。
この場合にすべきことも留年した学生と同じで
「落とした科目の中を優先度の高い順に整理すること」です。
大きく分けて
①「もう1回チャレンジすれば取れそうな科目」
②「もう1回チャレンジしても無理そうだが、卒業・進級には絶対必要な科目」
➂「もう1回チャレンジしても無理そうだが、他の科目でも替えが利く科目」
この3つに分けられるといいです。
問題なのは②が多いケースです。
この場合は早めに大学の支援センターや
大学生向け塾の助けを借りた方が良いので、無料相談(60分)などをご利用ください。
一方で①・➂の科目だけならば、自分1人と友人からの助けで乗り越えられるでしょう。
早めに対策を始めていくことが大切です。
進級できた人ならではの注意点
「単位は落としたが進級はできた」という学生ならではの注意点があります。
それは…
「再履修の科目」と「新学年の必修科目」の時間割が被る可能性があることです。
※再履修とは落とした科目を取り直すことです。
どちらも必修科目の場合、どちらを選ぶべきが迷うと思います。
ここでのアドバイスは「選べるのなら、再履修の科目を選んだ方が良い」です。
大学の科目は大半が学年が進むごとに専門性が増していきます。
これはつまり
「2年生の専門科目は1年生の専門科目を理解している前提」で進み、
「3年生の専門科目は2年生までの専門科目を理解している前提」で進むということです。
再履修の科目を優先して勉強することが、最終的には次の学年の科目の勉強に繋がるケースが多いのです。
このあたりはあくまで原則で、学部や落とした科目によって若干変わります。
自分が落とした科目の相談をしたい場合は無料相談をご利用ください。
シラバス等をみながら、学習相談員がお答えいたします。
留年してでも卒業する人が多い
留年が決まると
「親に申し訳ない…」
「留年費用を出してと言えない…」
「もう1度頑張る気持ちになれない…」
とメンタル面で落ち込んでしまう学生が多いです。
そうすると「親に迷惑をかけないように、退学しよう…」と考える生徒さんもいます。
その一方で、保護者の方は「留年してでも卒業してほしい」と考える場合が多いです。
これは卒業後と退学後の進路を比較してのこともあるでしょう。
現在の日本では大卒者と高卒者では生涯年収が4,500万円ほど変わります。
これは高卒者が卒業後にすぐに働く前提で計算されているので、大学を途中でやめた場合の生涯年収の差は5000万円以上となるでしょう。
どうしても留年で追加にかかる費用よりも大きな差が開いてしまいます。
また、就職先の選択肢の幅も変わります。
「親に申し訳ない…」
「留年費用を出すくらいなら大学を辞めるのも…」
このように考えるも分かりますが、現代の日本では留年をしてでも卒業した方がいい場合が多いです。
このことから留年をしたり、塾に通っても卒業をする人が増えているのだと思います。
1人で抱え込みすぎず
ご相談ください
落としてしまった科目を自分で克服するのが難しい場合、1人で抱え込みすぎずに無料相談をご利用ください。
マイゼミは「大学生のための塾」なので
「単位を落としてしまった学生」
「留年が決まってしまった学生」
同じような状況の大学生が多く相談に来てくれます。
「自分と同じ状況の学生が他にもいる」
「同じ状況の学生が苦手を克服し、卒業した実績がある」
そんなふうに思えるだけで気持ちが少し楽になることもあります。
(実際にマイゼミでは単位を落とした学生たちが通う中で、「毎年95%の単位取得率」を達成しています。)
1人では解決できなくても、専門知識のある先生達と2人3脚なら乗り越えられることもあります。
全国の大学に対応していますので、お気軽に質問や無料相談の利用をお待ちしております。
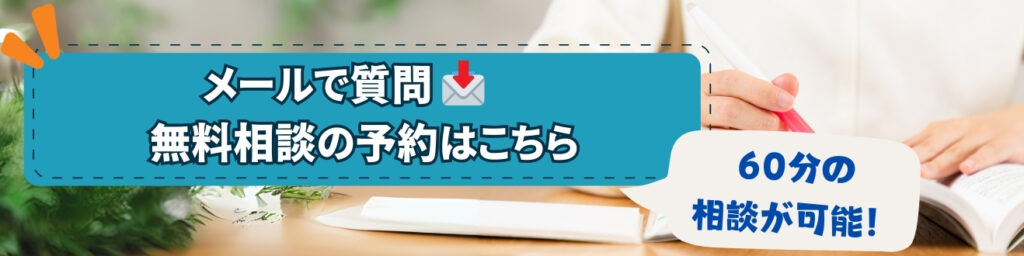
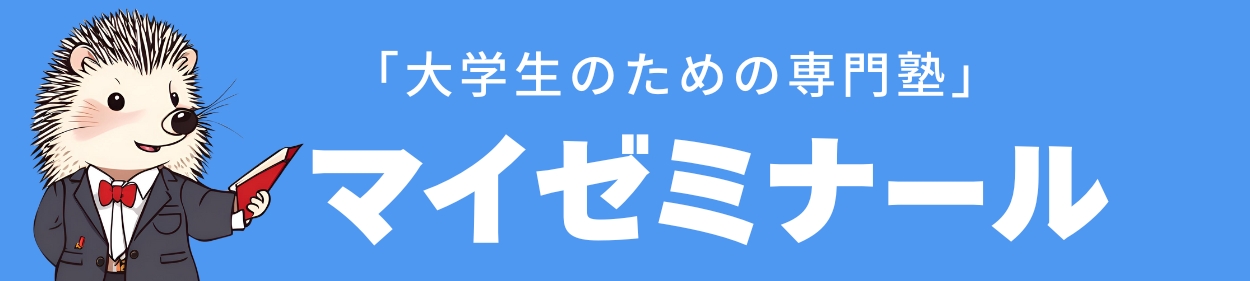



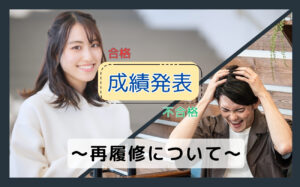
コメント