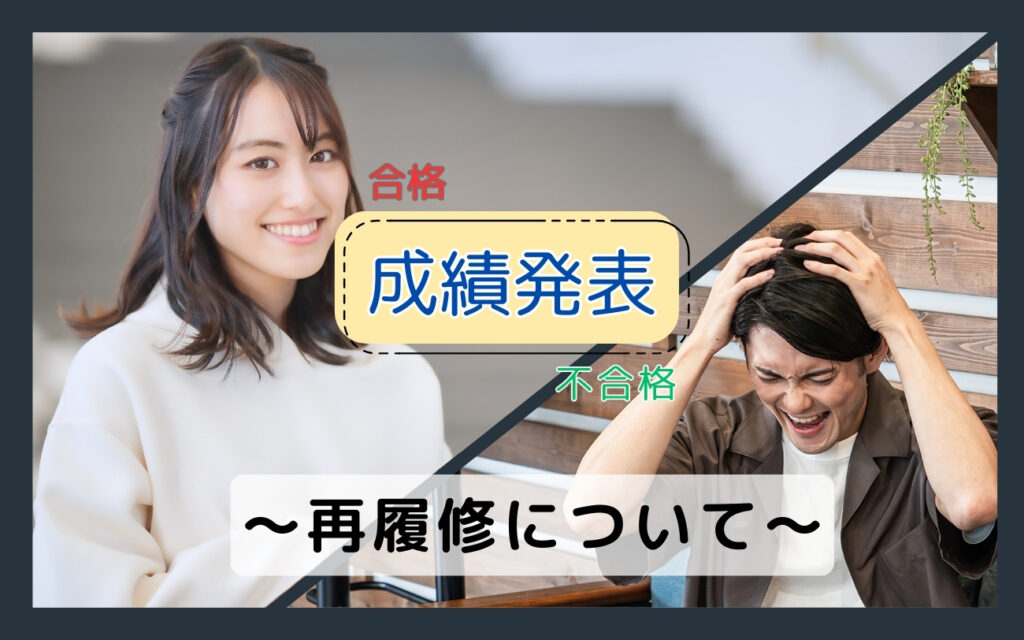
成績発表を受けて
そろそろ大学から正式な成績表が送られてくる頃ではないでしょうか。
WEBではすでに成績が確認できる大学も多いと思います。
(この記事は3月12日に書いています)
この時期は大学生が
「大学 単位 落とした」
「単位 落とした どうなる」
「単位 やばい 対処法」
「単位落とした 親に何て言う?」
このような検索をする子が増えます。
成績が良かった学生、思っていたよりも単位を落とした学生がそれぞれいると思いますが、単位を落とした学生にとっては不安な時期だと思います。
単位を落とした大学生はどうしたら良いのか、成績がでたこの時期に何をすべきなのかを1つ1つ整理しながら確認していきましょう!
大学で単位を落とした場合は
どうなるのか
「単位を落とす」とは受講した科目の成績が60点未満で不合格になった状態です。
(大学の科目は60点以上で合格になり、その科目を受講したことが証明されます)
60点未満で単位を落とした場合、今後どうしたらいいかを確認しましょう。
落とした科目が「必修単位」だった場合と「必修以外の単位」の場合に分かれます。
必修単位の場合
必修単位とは「卒業までに必ず取得しなけらばならない単位(科目)」です。
卒業までに避けて通れない科目なので「再履修」をしなければいけません。
再履修とは後輩たちに混ざってもう1度その科目を受けることを指します。
もう1度受講して、期末試験で60点以上を取れれば卒業ができます。
「ぎりぎり落としてしまって、もう少し勉強時間があれば…」
といった学生は翌年にもう1度チャレンジすることで取れるケースが多いです。
その一方で「全く分からなかった」「専門を3科目以上落としてしまった…」
こんな人は早めに大学の支援センターや大学生のための塾に相談しましょう。
選択必修の場合
選択必修とは、例えば「必修になっている12科目のうち、8科目以上を取ってください」というような制度です。
必修科目よりも少しだけ、自分で科目を選ぶ余地があります。
必修科目がA群・B群・C群などに分けられていて、それぞれの群ごとに〇科目中△科目を取るように、と言われているケースが多いです。大学ごとの履修要覧で確認しましょう。
(〇×群のような呼称は大学ごとに変わります)
選べると言っても、担当の先生の厳しさに相当の差がない限り、普通は「早く登場した科目ほど基礎的な内容になっていて、勉強しやすい科目」になっているケースが多いです。
落とした科目が選択必修の場合は「再履修をするのか」「この科目は諦めて、別の選択必修科目でチャレンジするのか」を選ぶことになります。
選ぶことはできますが、普通は選択必修の中から基礎寄りの科目から順番に履修します。
つまり、まだ受けていない別の選択必修科目はもっと難しい可能性が高いので、再履修する学生が多いです。
(特に理系学部はこの傾向が強いです)
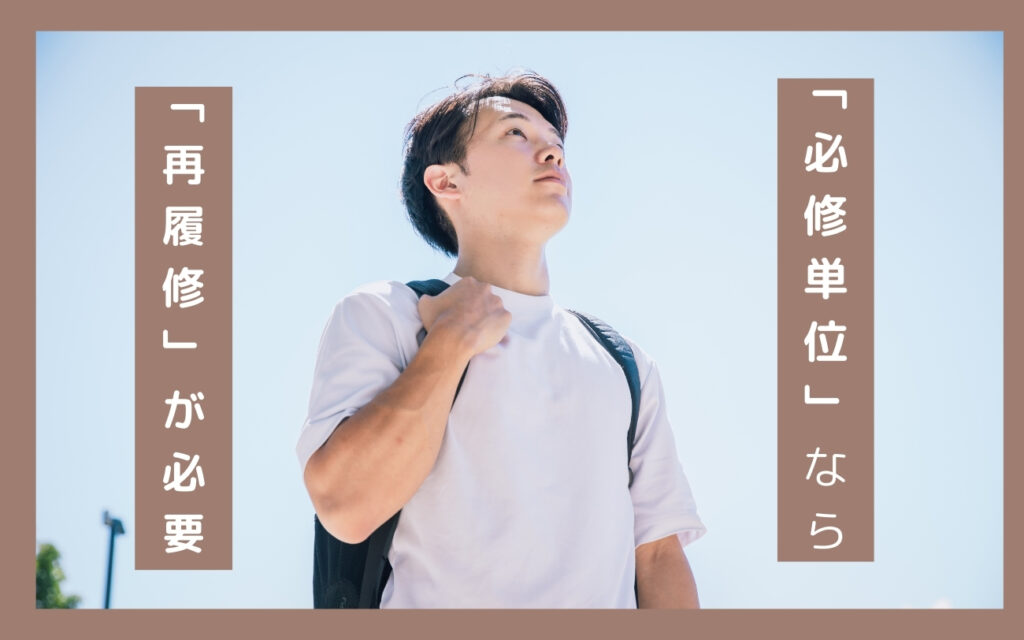
必修以外の単位の場合
大学の単位は「必修で〇単位、その他で△単位以上の取得」のように卒業要件が決まっています。
必修以外の「その他△単位」の部分が必修以外の部分です。
この部分は「必修単位で埋めてもいいし、教養科目で埋めてもいい」単位(科目)です。
必修や選択必修と比べると、どの科目を取るのかを自分で広い範囲で決められます。
教養科目を落とした場合は無理して再履修せず、別のジャンルの科目にチャレンジするのも有効です。
別の科目を取った友達や先輩後輩に聞いてみて、テスト対策がしやすい科目やレポートのみの科目を履修するのがおすすめです。
また、「この科目は興味が持てる。勉強が苦じゃなさそう」と感じる科目にチャレンジするのも1つの手段です。
まとめると…
「必修単位でなければ、無理して再履修せずに別の科目にチャレンジするのがおすすめ」
教養科目も「自然科学分野」「社会分野」などの各分野ごとに△単位以上取らなければいけない、と決まっている場合があります。履修要覧(入学時にもらいます)で確認しましょう。
医療系学部の場合
薬学部などの医療系学部はほとんど全ての科目を取らなければいけないことが多いです。
(落とした場合の留年規定も他学部よりも厳しめになっていることが多いです)
多くの医療系学部で落とした科目の再履修は必須となっていて、時間割の兼ね合いなどで大学からどのタイミングで再履修をするかなどの説明があるケースがほとんどです。
医学部・薬学部・看護学部の学生で再履修をしても合格できなそう…と感じたら
無料相談をご利用ください。

「再履修をする」となったら
確認すること
必修単位を落とすと「次こそはなんとしても合格しなければ…」と焦ると思います。
しかし、再履修の科目には初めて受講する科目とは違った注意点があります。
この段落では落とした科目を再履修して
もう1度チャレンジするとなった場合に気を付けることを紹介します。
いつ再履修をするのか
最初に確認してほしいことは再履修を「いつ」するのかということです。
前提として1度落とした科目は履修をしたときの記憶が残っているうちに再履修して合格した方が良いです。
「再履修の科目」と「新学年の必修科目」の時間割が被ってしまう場合です。
特に、研究室やゼミへの配属の関係で「新学年の必修科目」を優先しなければいけない場合もあります。
これは理系学部で起きやすいです。
落とした科目があると「すぐに再履修して取り直さなきゃ!」と感じると思いますが、大事なのは最短で「卒業」することです。
卒業には研究室に所属しての研究や発表が必要になるため、総合的に考えてどの科目を優先すべきかを考える必要があります。
そのような研究室などの縛りがない場合は落とした科目を優先した方が良いケースが多いです。
なぜ「落としたか」を思い出そう
単位を落とした科目は「なぜ落としたのか」を落ち着いて見返しましょう。
例えば…
・「あと少しで取れそう、もう少し時間があれば…」
このような学生と
・「正直、授業を聞いている時から理解ができなかった…」
このような学生では新学期からの対策方法は大きく変わります。
「あと少し」ならもう少しテスト勉強を早く始める、毎週の授業をこまめに復習するなど「自分でもっと努力する」ことで次は単位が取れる可能性が大きく上がります。
その一方で、「授業を受けたものの、ほとんど理解できていない」場合は次も1人で乗り越えられない場合が多いです。
この場合は早めに大学の支援センターや大学生のための塾を利用して、まずは「授業内容を理解」することが必要です。
落としたのが期末試験ではなく、レポート提出の科目の場合もあると思います。
マイゼミではレポート作成のサポートも行っています。
目先の科目のレポートに一緒に取り組みながら「レポートの作り方・まとめ方」なども学んでいきます。
最終的には1人でもできるようになるのが目標です。
1人で無理そうなら「早めに相談」しよう
「次も1人で乗り越えるのが難しそう…」
「単位を落とした科目の続きの科目が新学期から出てくる…」
このような場合は1人で再履修の科目を勉強し直して合格することが難しかったり、勉強し直してる間に続きの科目・派生の科目がどんどん進んでしまい、勉強が追い付かなくなるケースも少なくありません。
マイゼミではこのような状況の生徒さんのために無料相談(学習相談員との60分の面談)を行っています。
勉強に悩んでいる学生、1人でどうしたら良いか分からない学生、単位を落とした本人が落ち込んでいてどうしたら良いだろうと悩む保護者様、だれでも利用することができます。
お気軽にご利用ください。
再履修の科目が多い場合
優先順位を決めよう(時間割が被る場合)
さきほど「再履修の科目」と「新学年の必修科目」の時間割が被ってしまった場合について説明しました。
実際には再履修の科目どうしで時間割が被る場合もあります。
例えば「1年生で落とした再履修科目」と「2年生で落とした再履修科目」が両方とも火曜日の2限目に入ってしまったようなケースです。
このような場合、ほとんどのケースで1年生の科目を優先した方が良いです。
なぜなら「2年生の科目は1年生の科目で習った知識を持っている前提で授業が進む」ことが多いからです。
この傾向は「理系学部の生徒」と「経済学部の生徒」で特に顕著に表れます。
大学からの指定がある場合
大学から再履修の科目の優先度合について案内がある場合はそれに従いましょう。
落とした単位があまりに多く留年にする場合、医療系学部の場合は大学側から案内があるケースも少なくありません。
大学から指定がなく、研究室配属のために優先して取らなければいけない科目もない場合
①「新学年の必修科目よりも再履修の科目を優先」
②「若い学年の科目を優先」
(例:3年生で落とした科目より2年生で落とした科目を優先、2年生で落とした科目よりも1年生で落とした科目を優先)
この2つを基本として新年度の時間割を考えられると良いでしょう。
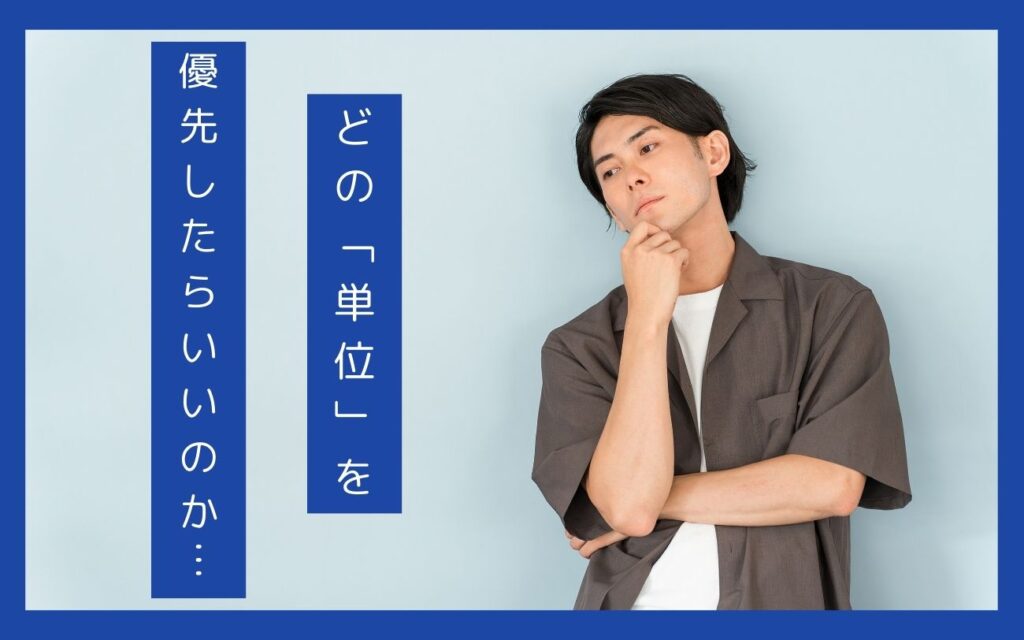
優先して取る科目の例
もしも1年生で落とした科目がたくさんありすぎて、どこから勉強したらいいか分からない。
このような場合は、「その科目の続きの科目」や「その科目から派生する科目」が多いものを優先的に勉強すると良いです。
例えば理系学部の生徒ならほぼ全員が履修する科目に「微積分」があります。
1年生の前期に習う「微積分1」を落とすと、その続きにあたる後期の「微積分2」も落としてしまう可能性が高いです。
これは後期の「微積分2」が前期の「微積分1」を分かっている前提で習う科目だからです。
大学の先生も「微積分1」で教えたことは理解している前提で授業を進めます。
(改めて振り返って教えることはしない先生がほとんどです)
また、微積分が終わると「微分方程式」などの派生科目が出てきます。
これも微積分の知識がない状態で勉強を進めるのは厳しいです。
また、これらの知識は数学だけではなく、物理科目の計算段階でも必要になるため、微積が全く分からないと物理科目も連鎖的に落としてしまうことが多いです。
このように1つの科目の理解がその後の多くの科目に影響してしまうことがあります。
このような基礎科目は優先的に勉強することをおすすめします。
勉強の順番で悩んだら…
「落とした科目が多くて悩んでいる…」
「自分はどの科目を優先して勉強したらいいのかな…」
このように悩んでいる場合はマイゼミの無料相談をご利用ください。
相談経験豊富な専門の相談員との「60分間の面談」で何でも質問ができます。
(予約制になっています)
詳しい情報やご予約は下記よりご覧ください。
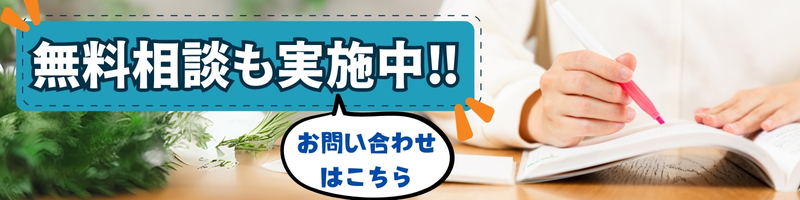
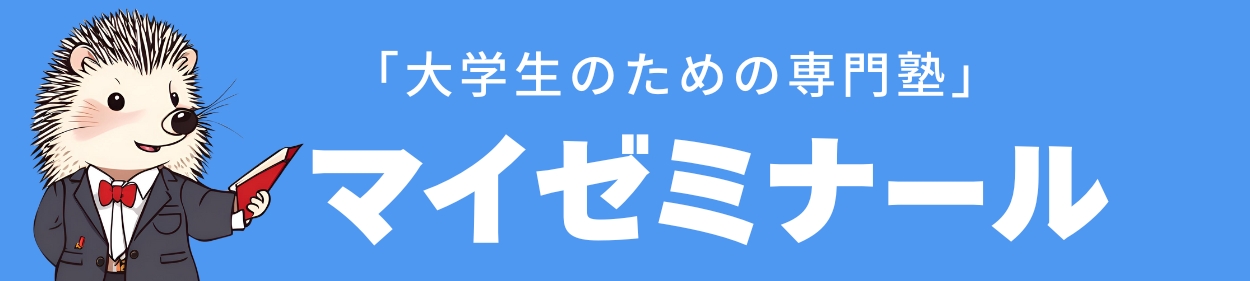


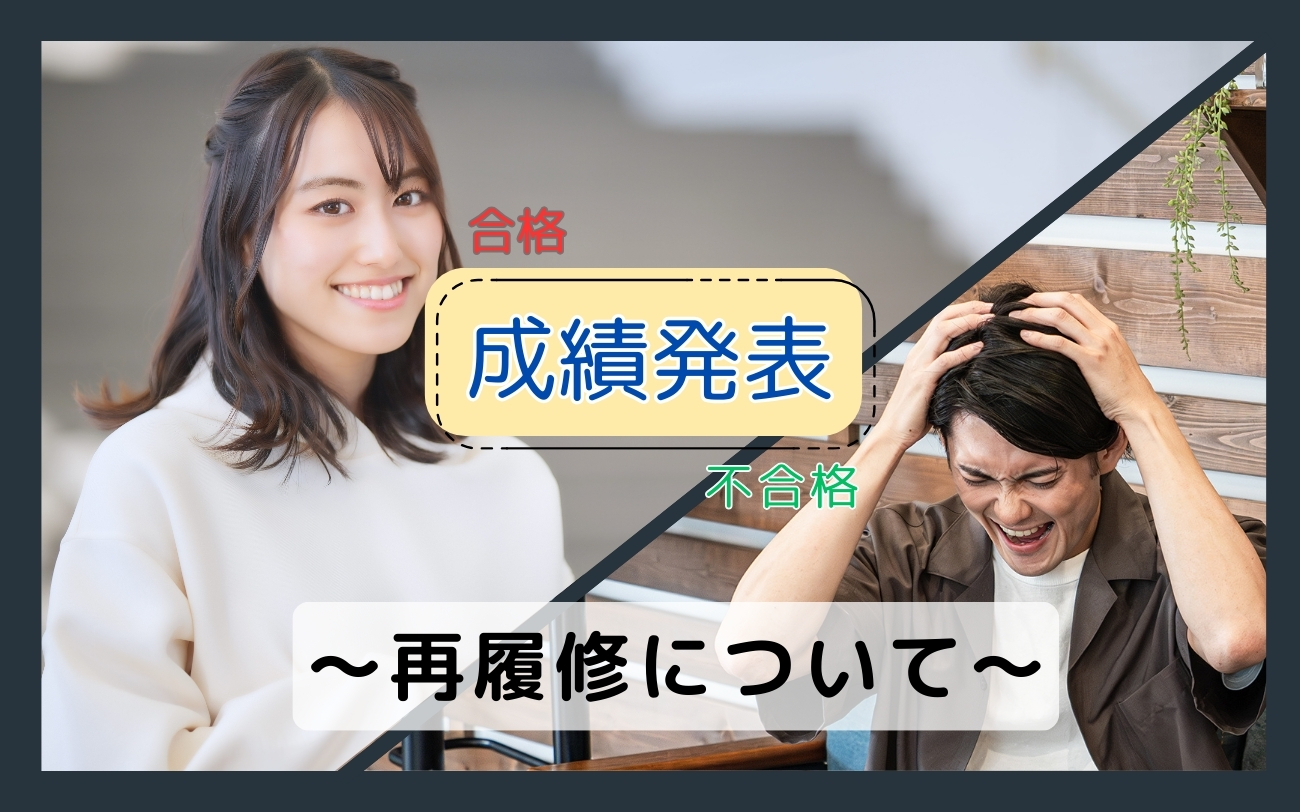

コメント